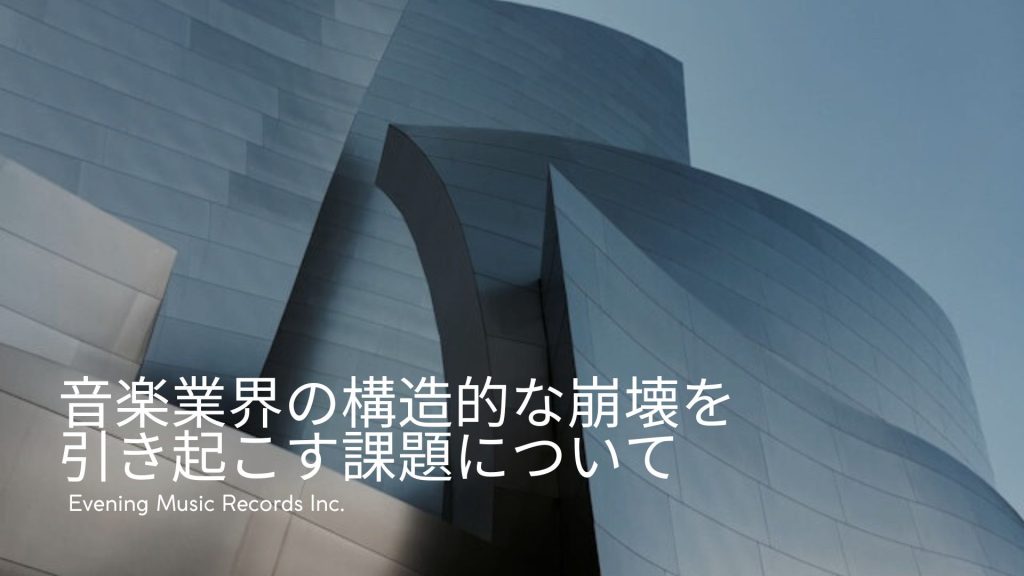公開日:2025年3月23日
近年、SpotifyやApple Musicなどストリーミングサービスの利用が世界的に広がり、音楽はいつでも、どこでも、誰でも聴ける「当たり前の存在」になりました。
グローバルチャートにはビッグネームが並び、TikTokなどのSNSではバイラルヒットが次々と誕生し、業界は表面的にはかつてないほど活況に見えます。
しかし、そのような表面的なトレンドの裏では、音楽業界が静かに確実に構造的に沈下しているという現実が進行しています。
特に、業界の土台を担う「中小アーティスト層」の離脱や疲弊に繋がる構造が、音楽業界の崩壊を引き起こしかねないポイントとして注目されています。
「開かれた音楽産業」の裏にある、持続不能な収益構造
確かに、音楽制作や配信のハードルは過去にないほど低くなりました。パソコン1台で誰もが世界へ曲を発信できる。まさに音楽の民主化といえます。
しかし、この“誰もが参加できる”時代において、皮肉なことに「誰もが継続できるわけではない」という新たな不平等が生まれています。
中小規模のアーティストは、ストリーミング1再生あたり0.3〜0.5円という極めて低い単価で収益を得ており、仮に10万回再生されても得られる金額は数万円程度です。
創作・制作・広報・ツアー・生活のすべてを自分で賄わなければならない独立系アーティストにとって、明らかに持続不能な構造です。
“裾野”が崩れれば、やがて“頂”も崩れる
現在の音楽ビジネスを支える存在として見落としてはならないのは、こうした中小アーティストこそが、実は音楽業界全体のエコシステムを支えている存在だということです。
- ストリーミングサービスにおける新規リリースの大半はインディーアーティスト
- アルゴリズムによる多様な発見体験も“裾野の豊かさ”があってこそ成立する
- 新たなスターは、無名の個人アーティストからしか生まれない
つまり、今の音楽産業は「トップ層」だけでは成立しない構造にあります。むしろ、巨大な非トップ層の活動と創造性があって初めて、トップアーティストが成立し、プラットフォームが健全に回り、リスナーが飽きない環境が維持されていると言えます。
しかし、この“支え手”たちが経済的に疲弊し、音楽シーンから離脱していけば、以下のような状況が生じる可能性が高いです。
- リリース楽曲数が減少する
- 音楽ジャンルが均質化する
- 新しい才能が発掘されなくなる
- リスナー体験が劣化する
- 結果的に、業界全体の競争力が失われる
短期的には気付きにくいレベルで、ゆっくりと音楽の多様性が失われていき、似たようなヒット曲に最適化された楽曲が配信ストアに並ぶといった未来が訪れる確率が高まります。
「音楽は無料でいい」という文化の代償
サブスク時代において、音楽は“背景音楽”や“BGM”としての存在感が強まり、価値が「無意識に消費されるもの」へと変質しつつあります。
これはリスナーにとっては快適な環境ですが、アーティストにとっては「創作価値に見合わない対価」という深刻な課題をもたらしています。
このような構造は、短期的にはサービスの利便性として評価されますが、長期的には創作意欲と多様性を奪い、音楽そのものの文化的な厚みを失わせていくリスクを孕んでいます。
今必要なのは、「続けられる構造」への転換
音楽業界がこのような構造的な課題を食い止めるには、一部のトップアーティストのみを支える構造ではなく、継続的に創作を行うことができるアーティストを支える構造への転換が必要です。
音楽業界のメジャーレーベルやスタートアップ企業では、すでにいくつか取り組みが進んでいますが、以下のようなアプローチを推進することが望ましいです。
- マイクロ支援の整備: ファン課金・教育連携・パトロンサービスの促進
- 収益分配モデルの刷新: ユーザー・セントリック・ペイメント(UCP)の本格導入
- アルゴリズムの再設計: 再生数至上主義から“エンゲージメント重視”への転換
- 地方・ローカルからの創作支援: 行政や地域文化施設との連携強化
音楽業界は、“見えない危機”に向き合う時期に来ている
音楽が「いつでも、無料で、すぐ聴けるもの」になった代償として、「誰がそれを創り、どうやって継続させるのか」は、見えにくい問題として放置されています。
しかし、そのような状況を放置した先には、「聴く音楽はあるが、創る人がいない」世界が待っているかもしれません。
音楽の価値を未来に繋げるために、この構造課題に正面から向き合う時ではないでしょうか。
本件に関するお問い合わせ
運営:Evening Music Records Inc.
Mail: info@evening-mashup.com
公式サイト:https://w3.evening-mashup.com/
※ 本リリースは、音楽業界の構造的課題に対する問題提起として、当社の見解に基づき作成されたものです。記載された内容は、現行の統計や公開情報をもとにした分析および当社独自の調査・視点に基づいており、業界全体や他事業者の公式見解を代表するものではありません。音楽文化の持続的な発展を目指し、議論と共創を促進する目的で公開しております。
©︎ Evening Music Records Inc.